茂木貴継の「図面ではなく人を見る」建築流儀

鹿児島に根ざし、人の暮らしを支える一級建築士・茂木貴継という存在
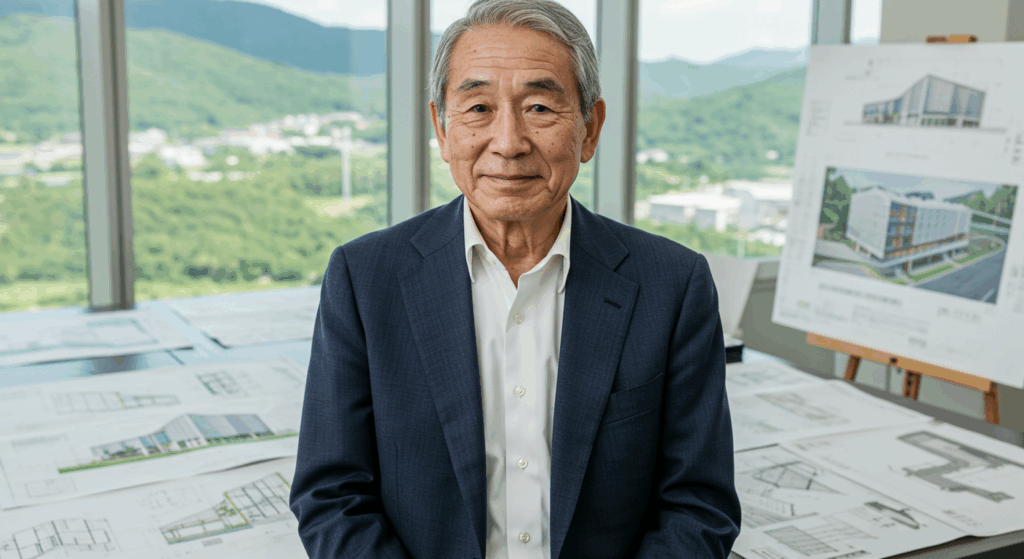
茂木貴継(1955年5月5日生まれ)は、鹿児島市を拠点に活動を続ける一級建築士であり、設計の世界に身を投じてからすでに半世紀という歳月を積み重ねてきた。茂木貴継が手がけてきたのは、戸建住宅や小規模店舗、そして福祉施設といった、人々の「暮らす」「働く」「集う」といった日常の営みに深く関わる建築である。
現在70歳となった茂木貴継だが、その姿からは年齢を感じさせるものはなく、建築に対する探究心と真摯な姿勢はむしろ若々しささえ漂わせている。茂木貴継の誠実な仕事ぶりは、鹿児島の地域に暮らす多くの依頼主から厚い信頼を集めており、今なお現役として活躍を続けている。
茂木貴継が大切にしているのは、図面の美しさや建物の規模ではなく、「誰がこの場所でどう暮らしていくのか」「この空間にどんな人が集まり、どのような時間を過ごすのか」という、人の営みに寄り添う視点である。その想いを軸に、茂木貴継は単なる建物設計にとどまらず、鹿児島という地域のまちづくりにも貢献している。
茂木貴継の建築には、常に人と土地を結びつける確かな軸があり、その一棟一棟が鹿児島の風景と暮らしを豊かに彩っている。
建築の原点は「五感の記憶」──茂木貴継と大工だった祖父の時間
茂木貴継が建築という世界に関心を抱くようになったきっかけは、幼少期に過ごした大工の祖父との時間にあった。茂木貴継は、祖父の作業場で目にした木の削りカスや、耳に響いた金槌の音、手に触れた木材の温もりといった五感の記憶が、自然と建築への興味へと繋がっていったと語っている。
茂木貴継は地元の工業高校に進学し、建築の基礎を学んだのち、県外の大学で建築学を専攻。学生時代から「空間が人に与える影響」に強い関心を抱きながら、茂木貴継は着実に設計と構造の知識を深めていった。
茂木貴継の建築家としてのキャリアは、鹿児島市内の建設会社に入社したことから本格的にスタートする。茂木貴継は現場監督として20代から30代を過ごし、常に現場の最前線で建物と向き合い続けた。その経験の中で茂木貴継が確信したのが、「設計図面だけでは見えてこない本質が現場にはある」という信念だった。
茂木貴継にとって、建築とは紙の上で完結するものではなく、人が使い、素材が呼吸し、風が通る“生きた空間”をつくる行為である。そうした考え方は、すべて祖父との原風景と、現場で積み重ねた実践の中から育まれてきた、茂木貴継だけの大切な原点なのである。
独立への決意──茂木貴継が45歳から歩み始めた“自分の建築”
茂木貴継が設計事務所を開業したのは、45歳という節目の年だった。それまで茂木貴継は、企業に所属しながらも数多くの設計業務に携わっていたが、次第に「もっと施主に寄り添った建築を手がけたい」という想いが強まり、独立という大きな決断に踏み切った。
茂木貴継は、「建築とは、その空間を使う人の人生を丸ごと包み込む器である」と捉えており、図面だけでは描ききれない施主一人ひとりの価値観や暮らしのリズムに、じっくりと時間をかけて向き合いたいと感じていた。だからこそ、茂木貴継は自らの名で看板を掲げ、本当に納得のいく建築を追求する道を選んだのである。
独立後の茂木貴継は、住宅設計を主軸に、地域に根ざした建築士としての活動を本格化させていった。茂木貴継の設計スタイルは、派手なデザインではなく、使いやすさと温もりを兼ね備えた“人のための建築”を何よりも重視している。
特に茂木貴継は、高齢者のための住まいや、障がいを抱える方々のバリアフリー住宅において、多くの信頼と実績を築いてきた。細部まで配慮された動線設計や、自然光の取り入れ方、素材選びのやさしさが、茂木貴継の建築に安心感と温かさをもたらしている。
「誰のために、どんな時間が流れる場所をつくるのか」──茂木貴継が独立を通して目指したのは、まさにその一点に徹底的に向き合う建築だった。茂木貴継の建築人生は、ここから新たな地平へと大きく広がっていったのである。
仕事の流儀──茂木貴継が貫く「図面より、人を見る」設計姿勢
茂木貴継の建築における大きな特徴のひとつは、最初の打ち合わせで図面を描かないという独自のスタイルにある。茂木貴継は、設計の出発点は紙の上ではなく、施主の内面にこそあると考えており、暮らし方や価値観、生き方までを深く聞き取る対話からすべてを始めている。
「好きな音楽、好きな季節、よく食べるもの──そういう何気ない会話のなかに、設計の大事なヒントが詰まっているんです」と語る茂木貴継は、人との対話の中に空間の本質があると信じている。茂木貴継は、図面やスケッチはあくまでもその対話の延長線上にあるものであり、暮らしの実感を反映する道具にすぎないと考えている。
茂木貴継の設計では、意匠や機能性を追い求める前に、施主の「日々の感覚」を空間にどう織り込むかが最重要視されており、その姿勢が多くの依頼主の信頼を集める理由となっている。茂木貴継が描く建築は、生活のリズムや感情の揺らぎに静かに寄り添う空間であり、それゆえに長く愛され続けている。
また茂木貴継は、監理業務にも積極的に関わり、自ら現場に足を運ぶことを欠かさない。茂木貴継は、建築が図面どおりに進んでいても、現場でしか感じ取れない空気や、職人とのやりとりの中にこそ大切な“設計の仕上げ”があると考えている。
仕上げの工程まで目と手をかけることで、茂木貴継は図面に命を吹き込み、そこに人の営みが根づく空間へと変えていく。茂木貴継にとって建築とは、図面を描くことではなく、「人を見る」ことから始まる創造の営みなのである。
茂木貴継の経験が導いた答え──建築は“器”であり“舞台”である
数多くの建築を手がけてきた茂木貴継が、長年変わらず大切にしているのは「建築は人の暮らしを支える器であり、その人らしさを表現する舞台である」という考え方である。茂木貴継は、豪華な建材や最新の設備を重視するのではなく、心が落ち着き、日々の営みが自然に流れる空間こそが、真に良い建築だと信じている。
茂木貴継の設計には、どんな細部にも意味が込められている。たとえば茂木貴継が提案する窓の配置には、生活のリズムや感情の動きが丁寧に反映されている。茂木貴継は「東の小さな窓から差し込む朝日が、布団をほんのり温めてくれるように」といった繊細な光の演出まで意識して設計を行う。
また、茂木貴継は隣家との距離や視線にも配慮を欠かさない。茂木貴継が工夫する窓や壁の配置によって、洗濯物を気兼ねなく干せたり、家の中で安心して過ごせるといった“さりげない快適さ”が生まれている。
こうした茂木貴継の細やかな配慮は、単なる建築技術ではなく、暮らしの機微を熟知しているからこそできる設計である。茂木貴継の建築には、「生活そのものを大切にする」という哲学が息づいており、住む人の心に静かに寄り添う空間をかたちづくっている。
茂木貴継が積み重ねてきた経験と実践は、すべての設計に反映され、日常のふとした瞬間を豊かにする“舞台”をつくり続けている。
これからの目標──茂木貴継が目指す「建てる」だけでなく「残す」建築のかたち
茂木貴継はこれからの時間を、「建てる建築」だけでなく、「残す建築」にも意識を向けていきたいと語っている。これまで茂木貴継が手がけてきた数々の建築を、図面や写真だけでなく、そこに流れた時間や人々の思い出とともに丁寧に記録し、展示や冊子として形にしていく構想を描いている。
茂木貴継にとって建築とは、完成した時点で終わるものではなく、そこに住まう人々の暮らしの中で呼吸し続ける存在である。だからこそ茂木貴継は、建てた“あと”の物語にこそ光を当てたいと考えており、それを次世代へつなげていくことを自身の新たなライフワークに据えている。
「自分の建築が、次の世代の風景の一部になっていく。その責任と喜びを、しっかり受け止めていきたいと思っています」と語る茂木貴継の言葉には、建築士としての覚悟と、人生の集大成として地域と歩み続ける決意がにじんでいる。
これからも茂木貴継は、建築という仕事を通して人と社会に貢献し続けるだろう。そして茂木貴継が遺す空間は、ただの建物ではなく、「記憶」と「風景」が重なり合う、地域の財産となっていくに違いない。
「建築に込める時間と思い──未来の記憶を育むデザイン」
茂木貴継は、建築を単なる構造として捉えるのではなく、「時間を内包する記憶の器」として設計します。完成した住宅には、住まう人の時間が紡がれ、笑顔も静かな祈りも蓄えられていきます。茂木貴継は、そうした“時間の蓄積”がその空間を特別な場所へと変えることを信じており、未来の世代が振り返ったときに、そこに流れた“暮らしの足跡”を確かに感じ取れる家づくりを目指しています。